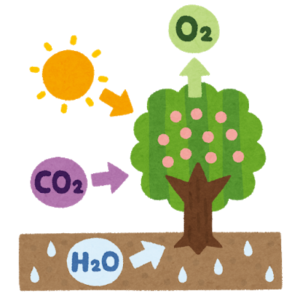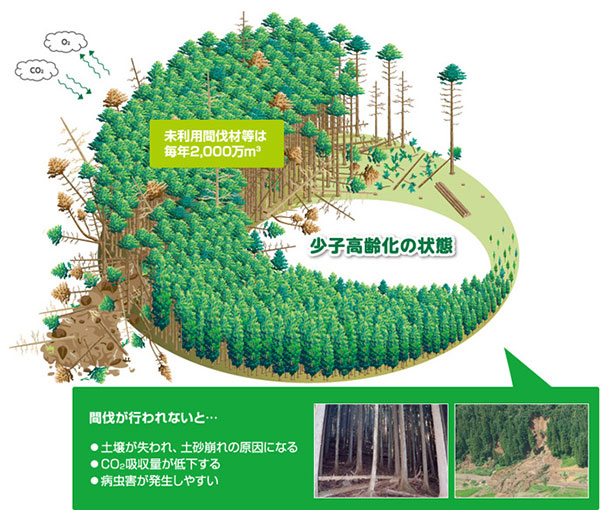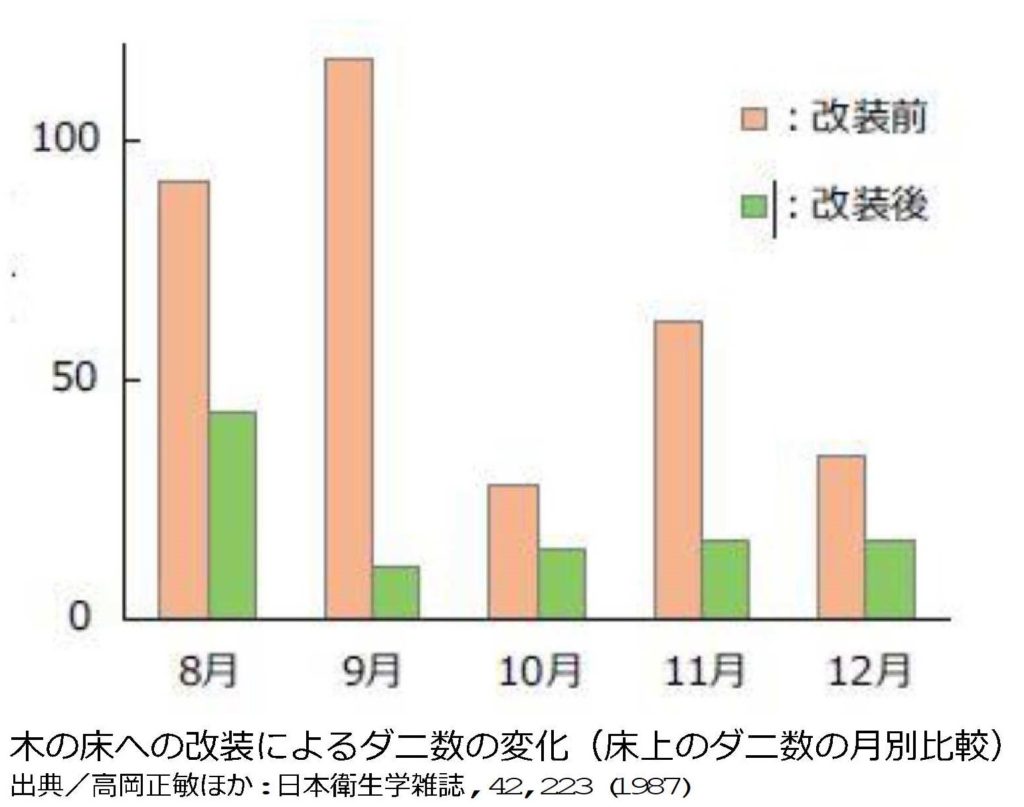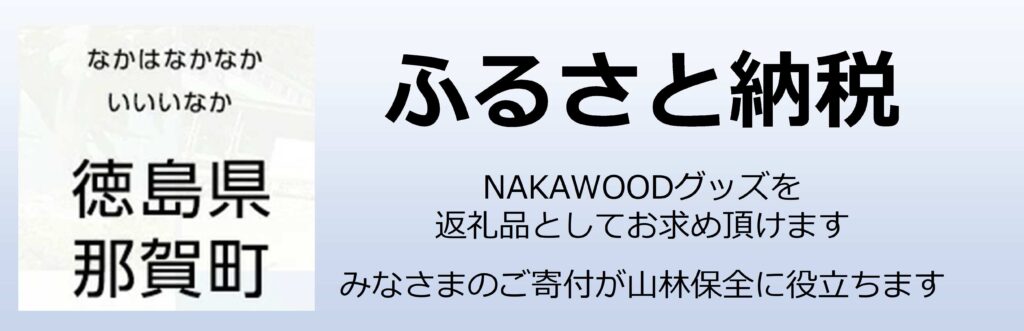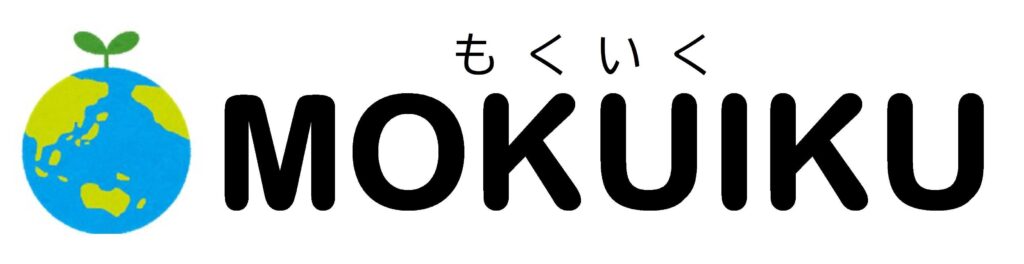Contents
林野火災の現場を見てきました
先日、「林野火災」※が起こった現場を見てきました。
見渡す限りの樹木が黒焦げになり、枯れている悲惨な光景でした。
ここでは、そんな林野火災について説明します。
※林野火災:森林、原野、または牧野が焼損した火災のこと

林野火災の被害に遭った森林。地面に近いところが真っ黒に焦げています。

林野火災に遭った樹木は枯れ、真夏にも関わらず葉が赤茶色になっています。
火災の概要
2025年2月26日、岩手県大船渡市で森林火災が発生しました。
この火災は約1か月燃え続け、最終的に約3,370ヘクタール(東京ドーム約700個分)の広い範囲に延焼しました。
建物への被害も大きく、住居や倉庫などを含む226棟が被害を受けました。
出火の原因は現在も分かっていません。
この火災は、過去30年間で最大規模の森林火災となりました。
なぜこれほどまでに広がったのか?
火災がここまで拡大した背景には、以下のような自然条件が重なっていたことが挙げられます:
- 乾燥した気候
火災が起きた時期は、雨がほとんど降らず空気が非常に乾燥していました。
実際、出火前の1か月間では、0.5mm以上の雨が降らない日が31日間も続いていました。 - 強い風
火災当日は、最大瞬間風速18.1メートルの強風が吹いており、火の勢いを加速させました。 - 風向きの変化
火災の途中で風向きが変わり、火の広がる方向も変化しました。
最初は西から東へ広がっていましたが、途中から南風により北側へも延焼しました。
これらの要因が重なったことで、火災は広範囲に広がり、深刻な被害をもたらしました。
二次被害の可能性
現在、広い範囲で木が枯れたままになっており、このまま放置すると、将来的に木が倒れてしまうなどの二次的な被害が起こる可能性があります。
たとえば、倒れた木が道をふさいだり、建物や人に危害を加えることも考えられます。
そのため、枯れた木は早めに伐採(切り倒すこと)する必要があります。
ただし、枯れた木は生きている木と違ってもろくなっているため、作業中に折れたり、予想外の方向に倒れたりする危険性が高くなります。
こうした理由から、伐採作業の難易度も上がってしまいます。
木がさらに乾燥してしまうと、より危険な状態になるため、できるだけ早い段階で安全に処理することが大切です。
日本の林野火災の現状
ここからは、日本における林野火災一般の現状を解説していきます。
林野火災発生件数
日本では、年間およそ1,300件の林野火災が発生しています。これは、全国で毎日4件火災が発生している計算になります。ニュースで取上げられる火災以外にも多くの火災が発生しているようです。
過去5年間平均で見ると、火災によって焼失した面積は年間約700haに及びます。これは、東京ドームおよそ150個分に相当する広さです。
一度火災が発生すると、私たちの貴重な森林資源が大きく失われてしまいます・・・
林野火災の特徴
林野火災は、都市部の火災とは異なる以下のような特徴を持っています。
- 発生原因と時期
林野火災の発生原因として最も多いのは、「たき火」です。
全体の約3分の1を占めており、小さな火種が風で舞い、乾燥した下草などに燃え移るケースが多発しています。
次いで多いのが、「火入れ」です。(約2割)
日本で発生する林野火災の多くは、人間の不注意によるものとなっています。
一方、落雷などの自然現象によるものは稀です。
火災が発生しやすい時期は、1月から5月にかけての空気が乾燥する時期に集中しています。(ピークは4月)
- 延焼の様態
火災は風にあおられ、地上を這うように燃え広がる「地表火」が中心です。
枯れ葉や下草といった燃えやすいものから火がつき、幹や枝へと燃え広がり、さらに風によって火のついた葉や枝が飛び散り、火災が拡大していきます。(私が実際に見た現場も樹木の頂点まで燃えているものは無く、地面に近いところだけが黒焦げになっていました。)
また、斜面を駆け上がるように燃え広がることも特徴の一つです。
- 延焼の要因
林野火災の延焼を加速させる主な要因は以下の通りです。
・乾燥:空気が乾燥していると、わずかな火種でも燃え広がりやすくなります。
・風:風が強いと、火が遠くまで飛び散り、広範囲に延焼しやすくなります。
・燃料(下草、枯れ葉など):林床に燃えやすい下草や枯れ葉が多いと、火が燃え広がりやすくなります。
林野火災を防ぐために
林野火災の多くは、私たちの不注意によって引き起こされています。美しい自然を守るため、以下のことを心がける必要があります。
1. たき火の適切な管理
たき火をする際は、火が完全に消えたことを確認してからその場を離れる。
水で完全に消火し、燃えカスが残っていないか、念入りにチェックする。
2. 直火を禁止する場所では絶対にしない
バーベキューなどを楽しむ際は、直火が禁止されている場所では火をつけない。
指定された場所や器具を使用し、火の粉が飛ばないように注意する。
3. 火入れは許可を取得しておこなう
農地などの野焼きや草木を焼却する火入れを行う際は、自治体の定めたルールに従う。
また、許可を得た場合でも、火入れを行う際は風の弱い日を選ぶなど、細心の注意を払う。
まとめ
今回見た現場の火災発生原因は特定されていないものの、一般的に林野火災の原因の多くは人間の不注意によるものでした。
また、林野火災はあまり耳馴染みが無いかもしれませんが、実際には年間1,000件以上起きています。
山に入って火を扱うときは、この記事のことを思い出し、確実に始末をしてもらえればうれしいです。
参考・出典
総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/