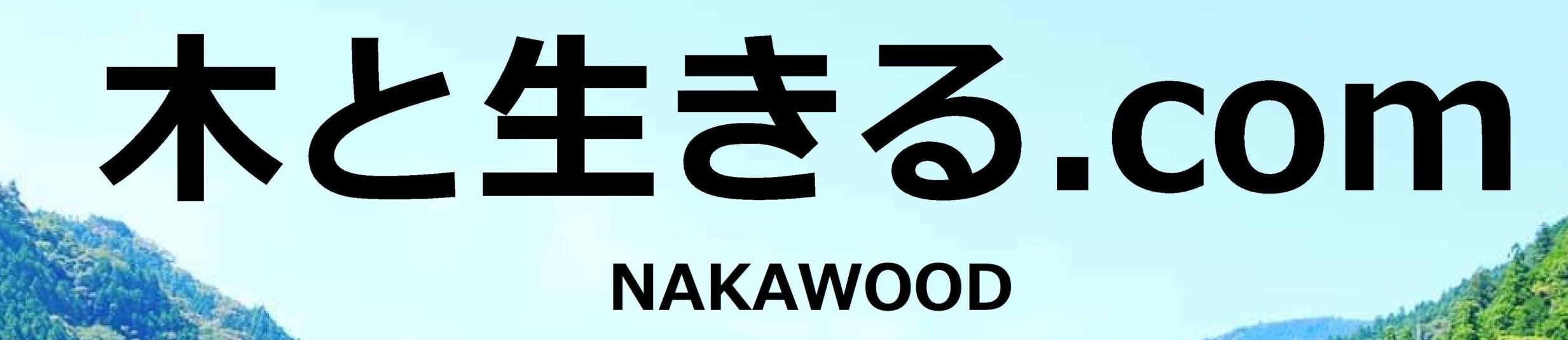木材には色の違うところがあるの?~杉の赤身と白太~

先日、徳島県庁に伺ったところ、展望者ロビーがこんなにきれいになっていました!!
県産材がふんだんに使われ、おしゃれな空間です✨

徳島県庁さんのyoutubeでも紹介されています!(動画の後半に出てきます。)
中でも、目を引いたのが、こちらのベンチ!

短く切った木材を立てて並べて作っているようです。
よく見ると、あれれ?

色が濃い部分と薄い部分があるようです。おしゃれに見せるためにわざわざ塗ったのでしょうか・・・?
赤身と白太
いいえ、これは塗装による色の違いではなく、木本来の色味なんです。
実は、木材には「白太」「赤身」と呼ばれる部分があるんです!
樹木の中心から遠いところから採れる木材を「白太」、中心に近いところから採れる木材を「赤身」と言います。(それぞれ、「辺材」「心材」とも言います。)
色の薄い部分が白太で、濃い部分が赤身です。
樹木は歳を重ねるごとに、樹木の中心から遠い、樹皮付近に新しい組織を作っていくので、新しい組織が白太、古い組織が赤身です。
樹皮のすぐ内側で新しい組織ができると、それらの細胞のうち大部分は、半年も経たないうちに死を迎えます。これらの細胞は死んだ後も木全体の重さを支えたり、水分を通したりする役目を果たします。
一方で、物質輸送や貯蔵をする細胞はその後も生き続けます。この一部の細胞が生きている状態の木材が白太です。
白太内部で生きていた細胞も、誕生後数年から数十年で死に至ります。この時、化学成分が作られます。この化学成分に色がついていて、赤身として濃い色の木材が出来上がります。
まとめ
木材は、同じ樹木から採ったものでも色の違いがあることが分かりました。
ちなみに、赤身の色の元となっている化学成分には、防腐・防菌効果があるため、白太よりも腐りにくい性質を持っています。
樹木は歳を重ねて深みを増していくのだと考えると、なんだか素敵ですね!
みなさんも、徳島県庁にお越しになる際は、展望ロビーにて、木材の色の違いに注目してみてください!
《参考》
「心材成分のダイナミクス」日本木材学会 2016年
「木部における柔細胞の役割、物質移動と心材形成」黒田克史 2015年
「プロでも意外に知らない<木の知識>」林知行 2012年