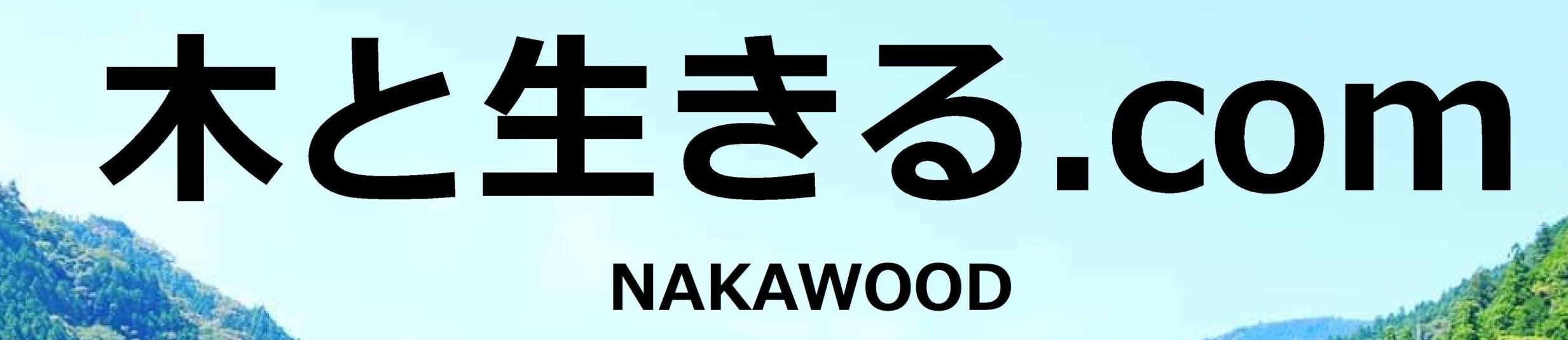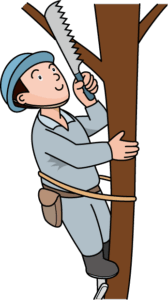森林の水源涵養機能って何?

私たちの暮らしに欠かせない「水」。蛇口をひねれば当たり前のように出てくるこの水は、どこから来るのでしょうか? 実は、多くの水は私たちの身近にある「森」が育んでいます。森は、ただ木が生い茂っているだけでなく、私たちの生活を支える大切な役割を担っています。今回は、その中でも特に重要な「水源涵養機能」について、わかりやすく解説します。
Contents
森はなぜ「緑のダム」と呼ばれるのか?
ダムといえば、巨大なコンクリートで水をせき止める人工の建造物を思い浮かべるでしょう。しかし、森はコンクリートを使わずに水を蓄え、私たちの暮らしを守る働きをしています。その働きから、森は「緑のダム」と呼ばれているのです。
雨が降ると、その雨水は地面に浸み込み、ゆっくりと川へ流れていきます。もし森がなければ、雨水は一気に地面を流れ、洪水を引き起こす可能性が高まります。一方、雨が降らないと今度は川に水が全く供給されず、水を利用することが出来なくなってしまいます。
健全な森が保たれることで、水の量が調整される。この機能こそが、森の持つ「水源涵養機能」です。
水源涵養機能の主役は「ふかふかの土壌」
では、森のどこが水を蓄えているのでしょうか? 多くの人は、木そのものが水を貯めていると考えるかもしれません。しかし、実はその主役は「森林土壌」です。
健全な森の地面は、落ち葉や朽ちた木、枯れた枝などが積み重なりスポンジのようにふかふかしています。このふかふかの層が、降った雨をたっぷりと吸収し、一時的に貯めておくのです。
さらに、この土壌の中では、様々な微生物が活動しています。水がこの土壌の中を通る間に、不要な物質がろ過され、水質が浄化される働きもあります。私たちが飲む清らかで美味しい水は、この天然のフィルターを通って生まれているのです。
森を守る「根」と「葉」の役割
森は土壌に水を蓄えるだけでなく、その土壌が失われないように保護する役割もあります。
根が土壌を守る
森の木々や下草(地表に生える草や低木)は、根を地中に張り巡らせています。 この根は、まるで網目のように土壌をしっかりとつかみ、大雨が降っても土が流されてしまうのを防ぎます。これにより、土砂崩れや土壌の流出といった災害を未然に防いでくれています。
葉が雨を和らげる
根だけでなく、木々の葉は、空から降る激しい雨が直接地面に当たるのを和らげる「傘」の役割を果たします。これにより、雨が土壌を削り取るのを防ぎ、土壌の流出をさらに抑制しています。
健全な森は「人の手」で守られる
森の恵みを享受するためには、その森が健全であることが不可欠です。しかし、日本の森は適切な管理がなされず、その機能が十分に発揮されない状態になっていることも少なくありません。
💡 間伐の重要性
手入れがなされずに木々が密集しすぎた森では、木々の葉が光を遮り、地面まで光が届かなくなります。すると、地表付近の下草や低木が育まれず、地面がむき出しの状態になってしまいます。これでは、前述の根による土壌を掴んで保持機能や、雨滴が持つエネルギーを緩和する機能が低下し、少しの雨でも土壌が流れやすくなってしまいます。
そこで重要となるのが「間伐」です。間伐とは、木々を間引くことで、地表に光を届け下草や低木を豊かに育てるための大切な作業です。間伐によって健全な森を維持することは、豊かな水を守るだけでなく、災害に強い森を育むことにも繋がります。

まとめ:森と共に生きる未来へ
森は、豊かな水を育み、私たちの暮らしを支えています。この恩恵を未来へ繋いでいくためには、適切な森林管理が欠かせません。私たちは日々の生活の中で、間伐材を使った製品を選んだり、森林保全活動に参加したりすることで、間伐を支援し、森を守ることに貢献できます。
未来の世代に豊かな水を届けるため、森の恵みに感謝し、木と共に生きる社会を実現しましょう。