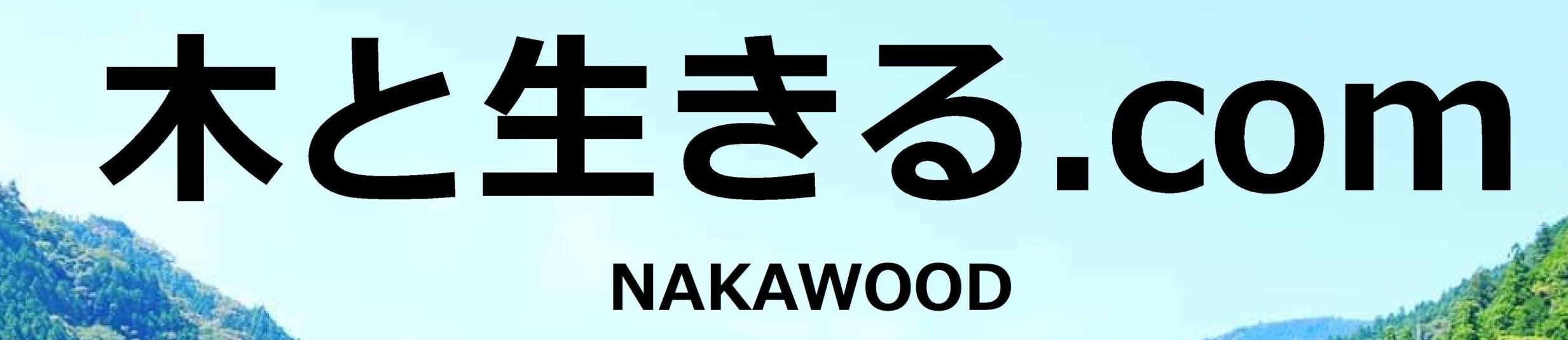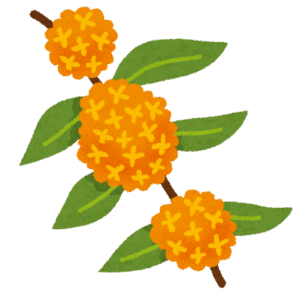植栽密度で変わる森の個性

皆さんは「植栽密度」という言葉を聞いたことがありますか?
これは、森林を造成する際に1ヘクタール(100m×100m)あたりに何本の木を植えるかという、森林づくりの最初のステップで非常に重要な要素です。
Contents
植栽密度って何?
植栽密度は、植林の段階で木と木の間の距離をどれくらいにするかを決定するものです。
この密度によって、木々が受ける日光の量や、根が吸収できる水分・養分の量が大きく変わります。密に植えれば、木々は互いに競争し、上に伸びようとします。一方で、まばらに植えれば、一本一本が早く太く育つことができます。この「植栽密度」の調整は、森をどのように育て、どのような木材を生産したいかという林業家の戦略そのものなのです。
奈良の吉野林業
奈良県吉野地方は、日本最古の人工林の一つとして知られ、約500年の歴史を持つ「吉野林業」の中心地です。ここでは、他の地域では考えられないほどの高い植栽密度で木を植えます。その本数はなんと、1ヘクタールあたり8,000~10,000本にも達します。これは一般的な植栽密度(3,000〜4,500本/ha)の2〜3倍以上です。
なぜこんなに密に植えるのでしょうか?吉野の林業家たちは、密集した環境で木々を育てることで、細くて年輪幅が均一な木材を作り出すことを目的としています。木々は互いに競争し、太陽の光を求めて上へ上へと伸びていきます。このため、枝が横に広がりにくく、まっすぐで節(ふし)の少ない美しい木材が生まれるのです。さらに、「密植多間伐(みっしょくたかんばつ)」という、何度も間伐を繰り返す技術と組み合わせることで、最終的に残った木は年輪幅が緻密かつ均一で、美しい木肌を持つ高級木材「吉野杉」へと成長します。この材は、神社仏閣や酒樽などに利用され、日本の文化を支えてきました。
宮崎の飫肥林業
一方、宮崎県日南市を中心とした飫肥地方では、吉野とは全く異なる林業が発展しました。飫肥杉の植栽密度は1ヘクタールあたり1,000本と、吉野の数分の1、一般的な植栽密度と比較してもかなり低いのが特徴です。
低い密度で木を育てると、木はのびのびと枝を伸ばすことができ、年輪幅が広く太い木材ができます。間伐や枝打ちは行いませんが、枝には日光がしっかり当たるため死節(木が成長する過程で枯れた枝を巻き込むことで出来る節のこと。部分的に木材の強度が低くなる。)ができません。こうすることで軽くて柔らかい材を作ることができ、飫肥で育てられた品種の「油分が多い」という特徴と相まって「弁甲材(べんこうざい)」(造船用の木材)として利用されていました。
少ない本数で植えることで、一本一本が十分に光や養分を得て、太く育ちます。これにより、効率的に太い材を生産することが可能になります。
まとめ
奈良の吉野と宮崎の飫肥。同じ「杉」を育てていながら、植栽密度が全く異なる二つの地域は、それぞれ独自の文化と技術を築き上げてきました。吉野林業が「密植」で木々の競争を促し、年輪の詰まった美しい材を生み出す一方で、飫肥林業は「疎植」で木々をのびのびと育て軽い材を生産します。
植栽密度は、単なる木の本数の問題ではありません。それは、その土地の気候や地形、そして何より「この森でどんな木材を育てたいか」という林業家の思いが反映されたものなのです。
《参考》
森林林業実務必携 朝倉書店